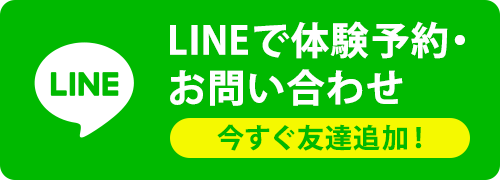『栄養について』
今回は、子供たちの健やかな成長を支える「栄養」について書かせていただきます。
本質的な目標は子供たちの健全な成長です。
その成長プロセスにおいて最も大切な3大要素は、①栄養 ②休養 ③運動です。
つい③運動にばかり目が向きがちですが、土台となるのは①栄養と②休養になり、順序としてもまず「栄養」が第一となります。
今回はその栄養について、「5大栄養素」→「子どもの体づくりのための栄養」→「サッカーに応用できる栄養」という流れでお話しできればと思います。
【5大栄養素について】
まずは「5大栄養素」について、簡単に整理します。
■ 炭水化物(糖質+食物繊維)
□ 脳と体を動かす速効性エネルギー。思考・判断・集中の土台となります。
□ ただし一度に摂りすぎると血糖値が急上昇し、その後急降下(血糖スパイク)を招き、眠気やイライラ、栄養素がうまく活用されなくなる原因につながります。
□ 目安:白米お茶碗1杯(約150g)=糖質約50g。一度に摂取する糖質量を50g以内に抑えるなど、量とタイミングの工夫が大切です。
■ 脂質
□ 長く安定して使えるエネルギーであり、細胞膜やホルモンの材料にもなります。
□ 良質な脂の例:青魚に豊富なオメガ3、オリーブオイル、MCTオイル、ココナッツオイル、バターなど。
□ 脂質をうまく利用するためには、ビタミンC・ビタミンB群・鉄・マグネシウムといった補助栄養素も必要です。
■ たんぱく質
□ 筋肉・臓器・皮膚・血液など、体を形づくる主材料。成長期には特に重要です。
□ 目安:体重(kg)×1〜2g/日。運動量が多い子どもは、体重1kgあたり約2gを目安にしっかり摂りましょう。
□ 不足すると、成長痛や疲労感など、体からのサインとして現れます。
■ ビタミン
□ 体内の代謝を円滑にする潤滑油の役割。直接エネルギーにはなりませんが不可欠です。
□ 例:ビタミンC(抗酸化・鉄吸収促進・免疫)、ビタミンB群(糖質・脂質・たんぱく質の代謝や神経機能を補助)、ビタミンD(骨の成長・免疫調整)、ビタミンE(抗酸化・血流改善)など。
■ ミネラル
□ 骨や歯の材料となり、神経や筋肉の働きを調整します。
□ 特に意識したいもの:マグネシウム(筋肉の弛緩・神経安定)、カルシウム(骨の密度維持)、鉄(酸素運搬・集中力向上)。
□ 食材例:マグネシウム=海藻・豆類・ナッツ・全粒穀物、カルシウム=乳製品・小魚、鉄=赤身肉・レバー・魚・貝類・大豆製品。
炭水化物(糖質)や脂質は、主にエネルギー源として働きます。
タンパク質は、身体を構成するための中心的な栄養素です。
ビタミンやミネラルは、体の機能や神経などの働きを支える役割を果たします。
それぞれの栄養素の働きを正しく理解し、バランスよく摂取することが大切です。
一点気をつけたいのは、栄養素はよく「樽」に例えられるという点です。樽は複数の板でできていますが、そのうちの1枚でも欠けると、中に入っているものはこぼれ出してしまいます。栄養も同じで、一つの栄養素が不足すると、他の栄養素が十分にあっても身体の機能は十分に働きません。
つまり、栄養を摂るうえで最も大切なことは、必要な栄養素を偏りなくすべて摂取することにあります。
【栄養素の吸収について】
次に「栄養素の吸収」についても触れておきます。
例えば、ある栄養素を10mg必要とする場合、吸収率が50%であれば20mg摂取しなければなりません。このように摂った栄養素がすべて体に利用されるわけではなく、一部は吸収されずに排出されてしまいます。
ここで大切なのが「親和性吸収力」という考え方です。これは、栄養の吸収率は一人ひとり異なり、さらに同じ人でも栄養素ごとに吸収効率が違うという分子栄養学に基づいた考えです。
ですので、単に基準量を満たせばよいのではなく、「親和性吸収力」を考慮して、各子どもに適した量を見つけていく必要があります。これは血液検査や尿検査で完全に数値化できるものではありませんので、眠気・イライラ・足がつる・肌荒れなど体の小さなサインを観察しながら、基準量から少しずつ調整していくことが大切です。
【分子栄養学に基づく摂取基準量(小中学生の目安)】
※分子栄養学(オーソモレキュラー栄養学)では「欠乏を防ぐ量」ではなく「細胞が十分に働ける量」を重視するため、一般的な基準より高めに設定されています。
・タンパク質:体重(kg)× 1〜2g
・ビタミンC:200〜1000mg(※1日数回に分けて摂取)
・ビタミンB群:10〜50mg(※B群複合体としてまとめて補給)
・ビタミンD:1000 IU〜1500 IU
・鉄:15〜20mg
・マグネシウム:300〜500mg
・亜鉛:15〜30mg
【糖質の摂取基準量について】
糖質は脳と体の主要なエネルギー源です。必要な量をしっかり摂る一方で、一度に摂りすぎないことがポイントになります。
一度に大量の糖質を摂ると血糖スパイク(血糖値が急に上がり、インスリンの大量分泌によりその後急に下がる)を起こし、眠気やイライラの原因になります。
一度の糖質摂取量を50g以内に抑えることが、健康管理の大きな鍵です。
現代社会では糖質の過剰摂取を防ぐことが最も難しい課題でもありますので、ぜひ意識してみてください。
■血糖スパイクが起きてしまう目安
一般的には、次のように考えられています。
・一度に糖質を60g(角砂糖約15個分、白ご飯で茶碗大盛り1杯分)以上、食物繊維やタンパク質を伴わずに摂取すると、血糖スパイクが起こりやすいとされています。
・子ども(小中学生)の場合は体格が小さいため、30〜40g程度の急激な糖質摂取でも血糖値が大きく上がることがあるとされています。
なお、「糖質◯グラムから必ず血糖スパイクが起きる」という明確な基準はなく、実際には個人の体質や食事の組み合わせによって大きく異なります。ただし、精製された糖質を一度に30〜60g以上摂取した場合、とくに空腹時や甘い飲料・菓子パンなどでは血糖スパイクが起こりやすい点には注意が必要です。
■注意点
特に練習や試合前には、血糖スパイクに注意が必要です。
血糖スパイクとは「血糖値の急上昇とその後の急激な下降」を指します。血糖値が急激に下がった状態では、体がエネルギーを十分に活用できず、集中力や持久力の低下を招いてしまいます。
練習や試合に臨む際は、適量の糖質を摂取し、体が正しくエネルギーを利用できる状態を整えることを意識しましょう。
せっかく摂取した糖質も、過剰に摂ってしまうとエネルギー化の働きが滞り、結果として体がフリーズしたように動きにくい状態を招いてしまいます。
【サッカーに応用した栄養】
体づくりの基礎(栄養の土台)ができたうえで大切になるのが「エネルギー代謝」です。
エネルギー源は大きく「糖質」と「脂質」に分かれます。
□ 糖質=速効型のエネルギー(主に脳・筋肉)。消費も早く、摂取のタイミングが重要です。
※ 脳は糖質(ブドウ糖)をほぼ唯一の燃料にしており、筋肉も瞬発的な動きでは糖質を優先的に利用します。
□ 脂質=持久型のエネルギー。主に筋肉で長時間利用されるほか、心臓や肝臓など全身の臓器でも活用されます。消費はゆっくりですが、長時間持続します。
※ 特に有酸素運動(長距離走、サッカーの走り込みなど)では筋肉のミトコンドリア内で脂肪酸が分解され、ATP(エネルギー通貨)がつくられます。
▼ 糖質がエネルギーになるまで
・液体(ジュース、スポーツドリンクなど):約10〜20分で吸収されエネルギーに。
・半固形(バナナ、エネルギーゼリーなど):約20〜40分。
・固形(おにぎりなど):約40〜60分。
▼ 糖質エネルギーの持続時間
・エネルギー化してから約1時間前後(激しい運動時は短くなることも)。
▼ 脂質がエネルギーになるまで
・摂取してから2〜4時間後に血中に放出され、エネルギー化。
▼ 脂質エネルギーの持続時間
・数時間〜半日以上(安静時や軽い運動では長時間持続)。
糖質は無酸素系(瞬発型)、脂質は有酸素系(持久型)と性質が異なります。糖質エネルギーで瞬発力を、脂質エネルギーで持久力を。両者を正しく理解し活用することで、子どもたちのパフォーマンスは確実に向上します。
練習や試合前には、糖質がエネルギーとして利用されるまでの時間、脂質がエネルギーとして利用されるまでの時間を逆算し、適切なタイミングで摂取することが、お子さまのパフォーマンス向上に直結します。
【脂質をエネルギー代謝する際に必要な栄養素】
脂質をエネルギー源として活用するのは主に「ミトコンドリア」であり、ここでβ酸化やTCAサイクル(クエン酸回路)が働き、ATPが産生されます。ミトコンドリアが十分に機能するためには、次の栄養素が不可欠となるため、しっかりと整理しておきましょう。
たとえ脂質を摂取していても、下記の栄養素が一つでも不足していれば、脂質によるエネルギー代謝はうまく機能しないため注意が必要です。
■ 鉄
■ マグネシウム
■ ビタミンC
■ ビタミンB群(特にB1、B2、B3、B5、B6)
■ タンパク質
【脂質代謝ができない場合の悪循環】
■ 脂質エネルギーがうまく使えない状態
ミトコンドリアが十分に機能せず脂質代謝が低下すると、エネルギー源として糖質に強く依存することになります。
■ 糖質エネルギーの特性
□ 速効性があるが持続時間は短い(約1時間前後)。
□ エネルギー切れが起こりやすく、体が「もっと糖が欲しい」とシグナルを出す。
■ 子どもによく見られる現象
□ エネルギー切れのサイン → 甘いものを欲しがる。
□ 血糖値の乱高下(血糖スパイク) → イライラ・集中力低下・情緒不安定。
□ 短い間隔で糖質を摂りたくなる → 糖質過多・栄養バランスの崩れ。
■ 結果として
糖質過多、栄養不足、イライラ、集中力欠乏などにつながります。これは現代の子どもたちに多く見られる典型的な栄養バランスの乱れの一因です。
脂質代謝がしっかり働けば、「糖質で瞬発力」「脂質で持久力」と役割分担ができるため、血糖値の安定や集中力の維持につながります。逆に脂質代謝が弱いと糖質依存に偏り、悪循環に陥るというメカニズムが生じます。
実際、脂質のエネルギー代謝が十分に行われていない子どもが多い印象を受けます。こうした背景を踏まえ、イライラなどのネガティブなサイクルを少しでも改善できるよう、そのメカニズムを正しく理解していただければ幸いです。
【サッカーの試合で必要なエネルギー量(糖質量)】
サッカーの試合で消費する糖質量は、年齢や試合時間によって大きく変わります。必要な糖質を適切に補給することで、最後まで集中力とパフォーマンスを維持できます。
□ 小学生(試合時間60分):糖質量/約35g必要
例:ポカリスエット500ml(約31g)+飴1個(約3〜5g)=約34〜36g
□ 中学生(試合時間80分):糖質量/約65〜70g必要
例:試合前 バナナ1本(約22g)+ハーフタイム ウイダーinエネルギー1袋(約45g)=約67g
小学生(試合時間60分)の場合、必要な糖質エネルギー量は約35gとなります。この量であれば一度に摂取しても糖質スパイクを起こす心配がないため、試合開始の10〜20分前にポカリスエットや飴などで補給するのが理想的です。
一方、中学生(試合時間80分)の場合は、必要な糖質エネルギー量が約60〜70gとなります。この量を一度に摂取すると糖質スパイクを招くため、分割しての摂取が不可欠です。試合前に30〜35gを摂取し、ハーフタイムに追加で30〜35gを摂取するなどの工夫が求められます。
また、糖質だけでなく脂質エネルギーの活用も大切です。脂質は主に筋肉で長時間利用される持久型のエネルギー源です。糖質が短時間での集中力や瞬発力を支えるのに対し、脂質は長時間の試合や連戦において持久力を維持する役割を果たします。したがって、糖質と脂質をバランスよく取り入れることが、安定したパフォーマンスの維持につながります。
【ホルモンと感情について】
気分や感情(幸せ・楽しい・悲しい・イライラなど)は、すべて体内のホルモンや神経伝達物質の分泌によって感じられます。例えば「幸せ」と感じるのは、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンやオキシトシンが分泌されるからです。つまり、気分や感情はホルモンが分泌された結果として生まれるものであり、「気分になってからホルモンが分泌する」のではなく、ホルモン分泌が先に起こるという点が要点となり、「ホルモンのコントロール=気分・感情のコントロール」となります。
■ セロトニン
□ 別名「安らぎのホルモン」。心の安定や安心感に関与します。
■ オキシトシン
□ 別名「愛情ホルモン」「絆ホルモン」。人との触れ合いや信頼関係を通じて分泌されます。
そして、これらのホルモンや神経伝達物質の材料となるのも、タンパク質やビタミン、ミネラルといった栄養素です。必要な栄養素が不足すると、ホルモンの合成が十分に行われず、感情の安定を保てずにネガティブなサイクルに陥ってしまいます。
一方で、ポジティブな気分や感情をつくるホルモンの材料となる栄養素をしっかり摂取できれば、ホルモンを適切にコントロールし、気分や感情もポジティブに整えることができます。
■ ホルモン合成に関わる主な栄養素
□ タンパク質
□ ビタミンC
□ マグネシウム
□ 亜鉛
□ ビタミンB群
どれか一つでも不足すれば、他が十分でも合成はスムーズに行われません。
子どものネガティブな感情の背景には、栄養不足が隠れていることが多々あります。
おわりに⸻
今回、子どもたちの健康と成長を願い、栄養についてできる限り分かりやすくまとめさせていただきました。
栄養学は科学の進歩とともに日々進化しています。数年後には、新たな発見に基づいて再びアップデートが必要になることでしょう。
この文章が、子どもたちが健康な体でエネルギーに満ちあふれ、笑顔でサッカーを楽しむためのきっかけとなれば、これ以上の喜びはありません。
子どもたちの健やかな成長が、やがてさらに素晴らしいサッカーライフへとつながっていくことを、心より願っています
YUコーチ